多様性理解勉強会 第03回「当事者研究」
講師
東京大学 先端科学技術研究センター 准教授
熊谷晋一郎先生
プロフィール:小児科医。新生児仮死の後遺症で脳性まひに、以後車いす生活となる。
東京大学医学部卒業後、病院勤務などを経て、現在は東京大学先端科学技術研究センター准教授。小児科という「発達」を扱う現場で思考しつつ、さまざまな当事者と共同研究を行う。

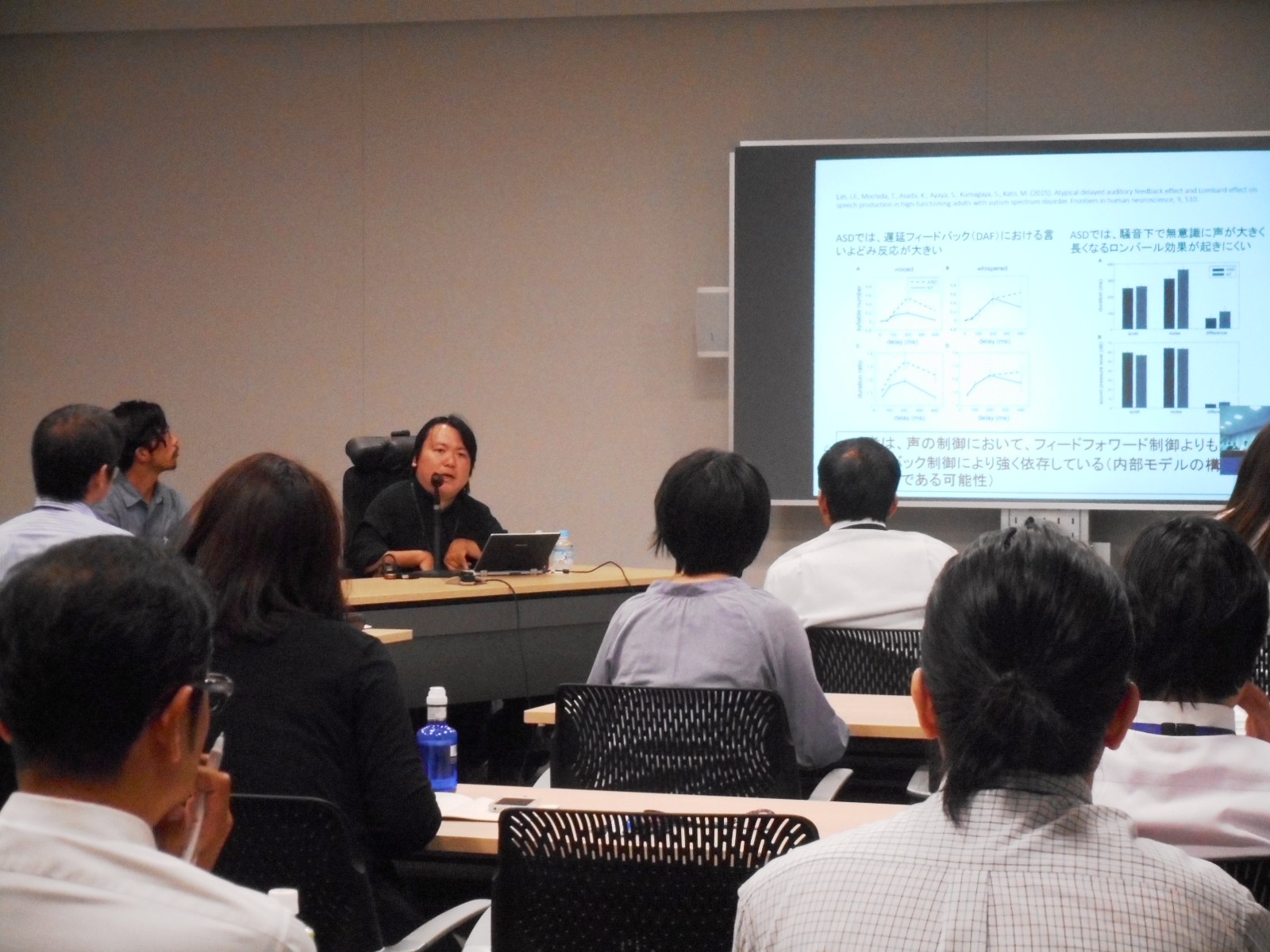
テーマ
「当事者研究」について
[当事者研究]とは
障害や病気を持った本人が、仲間の力を借りながら、症状や日常生活上の苦労など、自らの困りごとについて研究するユニークな実践です。
当事者研究は統合失調症を持つ人々の間で行われ始め、徐々に、依存症や脳性まひ、発達障害など、さまざまな困りごとを持つ人々の間に広まりました。
熊谷先生は、当事者研究が持つ仮説生成と検証、グループ運営技法、回復効果という、3つの側面に注目し研究されています。
講義内容
- 医学モデルと社会モデル~障害とは?障害はどこに宿るのか?
可変性に対する合理的配慮について - 社会と障害の共変化
- 自閉症向けの社会のデザイン
- コミュニケーションデザインの変化の方法論について
- 当事者にとって当事者研究に参加することが治療になる
受講者感想
これまでの自閉症の研究は、当事者ではなく、その周りの人を対象とした研究が多かったということです。
当事者の周りの人目線の意見を参考にしていることから、社会とのズレが大きくなっていることを学びました。
また、自閉症の症状も新たに知ることが多かったです。例えば、健常者よりも、カテゴリーを細分化する傾向にあること、そしてそれは、当事者を、追い詰める要素も持ち合わせていることを知ったときには、深く考えさせられました。「コミュニケーションは人と人との間に生じる」。これまで、個人の人柄だけでコミュニケーションを円滑にできると考えがちでしたが、この言葉を聞いて、はっとしたと同時に、納得できました。コミュニケーションは一人では行えないのです。



