Webコミュニケーション戦略設計から考える!経営を見据えたWebサイトリニューアルの裏側

株式会社DNPコミュニケーションデザイン
第3CXデザイン本部
課長補佐 清水 久美子/Kumiko Shimizu
「そろそろ自社のWebサイトをリニューアルしなければならない」「どのようにサイト制作を進行すべきだろうか」。そう悩んでいるWebサイト担当者の方も多いのではないでしょうか。DNPとDNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、こうしたWebサイト制作やリニューアルにおいても、数多くの企業に対しサポートを実施しています。
単なるWebサイト制作だけではなく、その前段階である「Webコミュニケーション戦略設計」に力を入れているのが当社の特徴です。そこで今回は、実例をもとにどのような手順でどのような取組みを行っているのかをご紹介します。
本記事でお伝えするプロジェクトは、重電機器や産業システム機器等を手掛けるBtoBメーカーである株式会社明電舎様のWebサイトリニューアルです。国内外に数多くのグループ会社を抱え膨大な数のサイトを持つ明電舎様の案件を、どのように進めてきたのか。その全貌とWebサイト制作に取り組む上で意識すべきことについて、担当の清水に聞いていきます。
1.「課題解決」と「経営目線の提案」がリニューアルサポートの鍵に
このプロジェクトの発足経緯をお聞かせください。
明電舎様は、グループ会社30社以上を含む多くのWebサイトを抱えている企業です。前回、明電舎様がヘッドクオーターのサイトをリニューアルしたのが2015年。当時は、BtoB企業であることやまだスマホ普及率がさほど高くなかったことを踏まえ、PCサイトをメインにリニューアルをされたそうです。しかしグループ会社や海外展開サイトなどの全サイトリニューアルを終えた5年後の2020年には、スマホ利用者がメインの時代に。デザインを含めて古い印象を受けるように感じられていたことに加え、デバイス変化やアクセシビリティ、クッキー規制を含むGDPR(EU一般データ保護規制)などに対応するため、そしてブランディングを強化していくため、改めてリニューアルプロジェクトをスタートすることになりました。
どのような経緯でDCDへの発注が決まったのですか?
明電舎様は、既に導入していたCMS「NOREN」をもっと活用していきたいという要望をお持ちでした。そこで、NORENを扱えるDCDが依頼先の一候補として挙がったのです。さらにこのとき明電舎様が重要視していたのは、「ブランディングの役目を果たせるサイトにするためにどうすべきか」を提案できる企業であること。最終的には、プラスアルファで提案した「経営にどう生かしていくか」という観点を評価いただき、当社でお手伝いすることになりました。また、先進的な取組みをしている他企業の事例を熟知していたことも大きかったようです。
プロジェクト全体の大まかな進行プロセスを教えてください。
ブランディングサイトと位置づけているコーポレートサイトを中心に、製品情報サイトについても一部変更を行いました。その後に国内外の関係各社のサイトを手掛け、順を追ってすべてのサイトをリニューアルしていくという流れです。DCDが全体のデザインガイドラインの設計を担い、外部の制作会社の方々にもご協力いただきながら関連サイトのリニューアルを実施しました。現在は明電舎様にお引渡しをし、明電舎様にてプロジェクトを進行されています。
2.「誰に・何を・何のために」の定義が設計のベース
Webコミュニケーション戦略設計は、どのように進めていったのでしょうか?
まずは「サイトをどう使っていくか、どう経営に生かしていくか」の定義からスタート。明電舎様へのヒアリングを経て、以下の3つの目的にたどり着きました。1つめが社外に向けて企業のイメージやスタンスを浸透させるコーポレートブランディング、2つめが製品情報を整理し売り上げにつなげていくマーケティング、3つめが国内外の全グループ会社を「ひとつの明電舎」として社員一人ひとりが認識し誇りを持てるようにするインナーブランディングです。これらをベースとしてサイトを設計しましょう、というお話をしました。
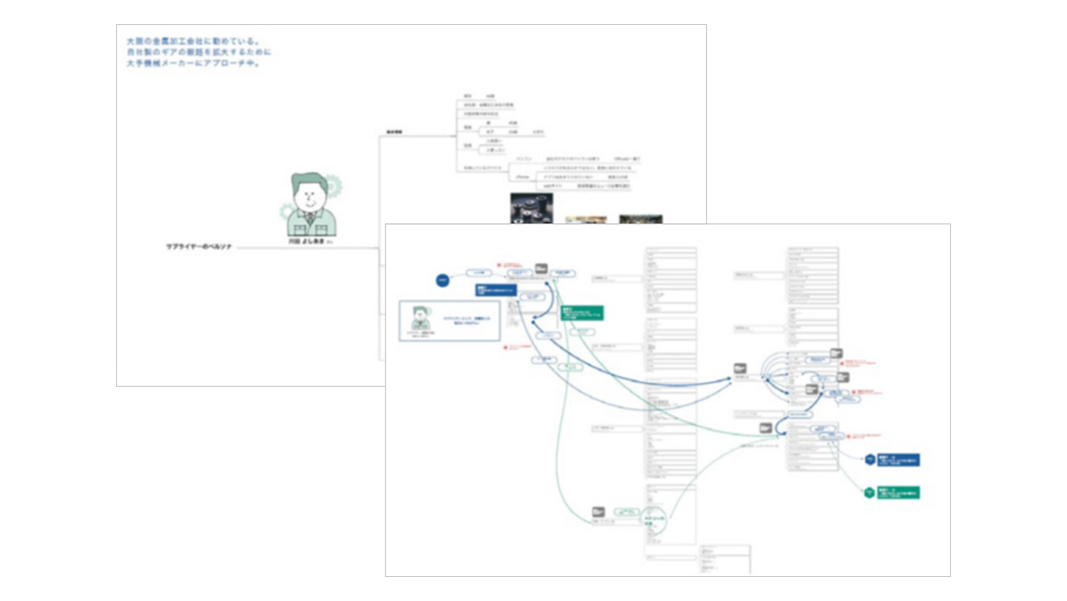
まずは目的を具体的に設定する。その上で次は何を考えていくべきなのでしょうか?
ターゲットを設定していきます。例えば、製品を使いたい顧客、株主投資家、社員、就活生、地域住民などですね。そしてその人は何を目的としてサイトを訪れるのか、何の情報を取得したいのかを整理します。「製品を使いたい顧客」の場合でも、「新規で購入を希望している顧客」か「既に製品を活用していてメンテナンスをしたい顧客」かで、目的は大きく異なります。この細かな分類も含めてそれぞれの目的を設定することで、やっとどの情報をどこに置く必要があるのかが見えてくるのです。
しかし考えるべきは、閲覧するユーザー側の目線だけではありません。反対に明電舎様側は、どんな情報をプラスで持ち帰ってもらいたいのか、どんなイメージを持たれたいのかといった「企業側の狙い」も明確化していきます。ユーザーと企業の目的が両方とも満たされるサイトこそ、最も良いサイトであると考えているためです。
サイトとユーザーとの間でのコミュニケーションが設計できてはじめて、コンテンツ精査に移ることができるのですね。
はい。既存のサイト内でどのコンテンツを残すべきか、どの情報を増やすべきか……その精査を踏まえて、優先順位をつけていくのが次の工程です。ただ今回、スケジュールがかなりタイトであることやページ数が膨大であること、予算が限られていること、複数の専門CMSが組み込まれていること……など、いくつもの懸念点がありました。そこで、リニューアルすべきページとそうでないページを分け、さらに明電舎様が従来依頼していた制作会社にサイト制作や運用を引き続きお任せすることで、全体の工数のスリム化や効率化を図りました。
3.企業の考えを体系的に伝えることで「理解と共感」を生む

( https://www.meidensha.co.jp/rd/ )
特に大きく見直したのはどのページでしょうか?
企業情報や研究開発、サステナビリティ、株主・投資家情報、採用情報といったコーポレート系のページです。それぞれ言及内容は違いますが、基本的にはどれも近しい考え方で構成しています。
一般的に多いのは「今実施している取組みのみ」に言及するパターン。しかし今回のリニューアルでは、企業としてどのような考えをベースとして取り組んでいるのかの「思考」、今後どうなっていきたいかの「未来像」を踏まえ、体系的に情報を構成しています。これにより、明電舎様の価値観や行動原理を読み手により明確に伝えることができるので、理解や共感、応援を得やすくなると考えています。特に研究開発のページは、より未来に向けた取組みを伝えるべき場所。だからこそ企業の姿勢を前面に出すことは非常に重要だと思っています。
ヘッドクオーターサイトをリリースして、どのような反響が得られましたか?
明電舎様からは、「社外の方から、体系的になってすごくわかりやすくなったと言ってもらえた」という声をいただきました。明電舎様が目指している方向と実際の取組みをしっかり整理するよう心がけていたので、狙い通りの評価がいただけたと感じています。
4.経営目線で考えたWebコミュニケーション戦略設計を

今後、企業のWebサイトはどう変化していくと考えていますか?
過去には「とにかく会社のサイトがあればいい」という時代もありました。しかし今は、「経営の観点でいかに戦略的に活用していけるか」まで考えなければ淘汰(とうた)されてしまう時代。Webサイトは企業が利益を上げ成長していくためのひとつのツールであり、この位置づけは今後も変わらないと思います。
ただ本案件がそうであったように、時代によって変化する閲覧環境への対応はこれからも必要です。また今後より大きく展開されるであろうパーソナライズされたコミュニケーションやAIを活用した対話への適応も重要になるでしょう。さらに法改正により、アクセシビリティ対応も日本国内でも強化されていくはずです。結局Webサイトは、ユーザーとコミュニケーションを取る場。だからこそ、社会環境の変化への適応は不可欠となるのです。
Webサイト制作やリニューアルを考えている企業に向けて伝えたいことをお聞かせください。
やはり「企業経営目線で見た目的の設定」と「目的達成のためのサイト設計」の明確化は非常に重要です。もちろんここをかなり熟考している担当者もいますが、まだ「何となく」で進めてしまっている方も多いのが実情ですね。また、担当者の目線だけだとどうしても「どう売るか」のマーケティング視点が強くなり、長期的でマクロな経営視点での検討が欠けてしまうことも多いんです。これはものすごくもったいないこと。
その担当者がサイトとして外に出したものはすべて、「企業として世に発信しているもの」として見られます。「売る」だけに目を向けるのではなく、「サイトは経営を見据えたコーポレートブランディングの場である」ということをぜひ意識してもらいたいですね。
- 2024年4月時点の情報です。
Webサイト制作やリニューアルをご検討中の皆さま、以下のサービスページでも詳しくご説明していますのでぜひご覧ください。



