深化するコミュニケーション。「企業カレンダー」から広がる、顧客に届くコーポレートブランディング戦略

(上段左から)三浦 賢一/Kenichi Miura、中城 海図/Kaito Nakajou、三浦 章正/Akimasa Miura、川口 真由子/Mayuko Kawaguchi、主幹企画員 川口 佐久良/Sakura Kawaguchi、(下段左から)井関 薫/Kaoru Iseki、髙井 望夢/Nozomu Takai、立川 聰子/Satoko Tachikawa、課長 姫野 美貴/Miki Himeno
DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)はその前身から、企業カレンダーの制作に注力してきました。DNPグループ企画部門の中でも、長い歴史を持つ企画制作チームです。毎年多くのご相談をいただいており、中には何十年と継続して手掛け続けている案件もあります。その評価のカギは一体どこにあるのか、現在のカレンダーチームに聞いてみました。
1.カレンダーは良質な「コーポレートブランディング」のツール
「ただ日付を確認できるだけのメディアだったら、企業カレンダーはもっと衰退しているはず」そう語るのは、長年カレンダーのクオリティを高めることに尽力している、匠デザイン室の川口 佐久良です。
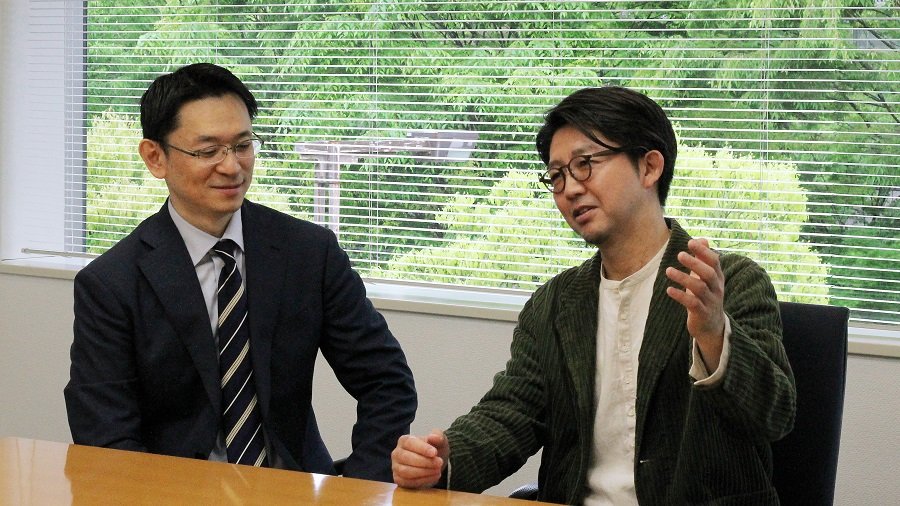
川口(佐):ひとり1台スマホを持ち歩くのが日常になった昨今、カレンダーの機能はほとんどのスマホに内蔵されているため、それで事足りてしまいます。にもかかわらず、DCDのカレンダーチームがクライアントに評価いただいているのは、カレンダーを“顧客に届くコーポレートブランディングツール”へとアップデートさせてきたからだと自負しています。
企業が今、どんなメッセージを世の中に届けたいのか。それをどんなビジュアルで表現するのが最も効果的なのか。その先で、顧客とどんなつながりを育てていきたいのか。そうしたことを、クライアントと丁寧に対話しながら、チーム一同日々の制作に当たっています。
さまざまなメディアが乱立している世界で、カレンダーはなぜ“顧客に届くコーポレートブランディングツール”になり得るのでしょうか。その理由について、三浦 賢一は次のように説明します。
三浦(賢):企業カレンダーは、大きく3つの役割を持っています。1つ目は、年末に顧客への感謝の気持ちを伝えるための「ノベルティ」。2つ目は、社会へのメッセージを包含する「文化活動」。そして3つ目が、先ほどの話にも出ていた「コーポレートブランディング」です。
カレンダーは、日々の生活に馴染(なじ)んで寄り添う存在であるからこそ、顧客の共感や信頼感の醸成に活用できます。企業の特性と、販促や文化活動としての機能も持たせながら、企業の思想や今後のビジョンを顧客と共有できる優れたコミュニケーションツールだと感じています。
2.コンセプト設計から印刷の現場まで、各工程で発揮されるプロとしてのこだわり
会社と顧客のよりよい関係構築に寄与できる、コーポレートブランディングツールとしての企業カレンダー。その制作に当たる現場のプロフェッショナルたちは、どんなこだわりを持って日々の業務に向き合っているのでしょうか。チームの若手である髙井 望夢は、具体的な制作に進む前段階の「コンセプトの擦り合わせ」に、大きな介在価値を感じていると言います。

髙井:事前の打ち合わせでは、クライアントから「こういうビジュアルにしたい」というイメージを先に提案していただくこともありますが、それをそのまま採用するとは限りません。クライアントと丁寧に対話を重ねていくと、顧客とのコミュニケーションにおいて、今どんな課題を抱えているのかが見えてきます。それを丁寧に探って、「課題解決に寄与するビジュアル、構成とは何か」を考え、芯を捉えた訴求シナリオやコンセプトを提案できるよう心がけています。
また、クライアントが周年などの節目を迎えるタイミングは、リブランディングの好機なので、一層気持ちがこもりますね。積み重ねられた歴史を振り返りながら、企業の真の価値を言語化し、それを今の時代にあった新しい表現で社会に届けるにはどうしたらよいか、私たちのチーム全員がクライアントと一丸となって、時間をかけて考えていきます。
真摯(しんし)な対話によって導き出された表現コンセプトを土台に、カレンダーは実制作へと進んでいきます。チームのリーダー的存在である三浦 章正は、クライアントの伝えたいブランドメッセージを最高の形で表現に落とし込むためには「弛(たゆ)まぬインプットとアップデート」が不可欠だと語ります。
三浦(章):カレンダー制作ディレクションの肝は「目利き」にあると言っても過言ではありません。企業が伝えたいメッセージをビジュアル化していく中で、目利きとしての「分析力」や「直観力」を最大限に発揮して、カレンダー=企業の顔として自信を持って世に出せるものを作るのが、私たちの仕事の根幹といえます。
だからこそ私たちは、日々のインプットが何よりも大事だと思っています。写真やイラスト、アートなど本物に触れ、感動し続けること。そして、常に新しいもの、文化に触れることを厭(いと)わず、自分の価値観もアップデートしていくこと。こうした地道な積み重ねが、的確なアートディレクションの礎となります。
緻密なコンセプトの設計と、その訴求力を十二分に引き出すための表現の飽くなき追求。さらにここに加わるのが、自分たちの真骨頂とも言える「印刷」へのこだわりだと話すのは、井関 薫です。
井関:ブランドイメージにつながる企業カレンダーにおいて、企画段階で想定していた色調などがイメージ通りに出ているかは、クリエイティブ全体の品質を左右する重要な要素です。DNPグループにはプリンティングコーディネイターという修整方向を現場に翻訳して伝える印刷のプロがいますが、それでも私たちディレクターはできるかぎり印刷現場まで足を運び、仕上がりを自分の目で確認します。「クライアントの意図したメッセージが、最大限伝わるアウトプットになっているか」の最終判断は、コンセプト設計から伴走しているディレクターの責務です。各現場を連動させ、一貫してアートディレクションしていくからこそ、クライアントにも、その顧客にも喜ばれるカレンダーを提供できるのだと思います。
また、カレンダーチームでは基本的にクライアント1社につき1人のディレクターが専属になりますが、それぞれの得意分野の知識、経験をチーム内で常時シェアしながら全員で協力して制作を進めています。キャリアの長い先輩たちに技術的なフォローを受けることもあれば、私たちのような若手がトレンドにまつわるアイデアを提供することもあり、こうしたフラットなコミュニケーションが良質なクリエイティブを支えているのだな、と実感しています。
3.紙だけでは終わらない。顧客のニーズに高いレベルで応える「多メディア展開」の企画力
DCDのカレンダーチームの強みは、企業カレンダーの制作だけにとどまりません。アート思考や自身の持つネットワークを積極的に活用する中城 海図は、カレンダーを起点とした「顧客とのハイブリッドなコミュニケーション」の提案を得意としているところにも、DCDは大きな強みがあると言います。

中城:私たちはカレンダーを印刷メディアだけで終わらせるのではなく、動画やWeb、さらにはリアルでの場づくりにも活用し、より効果的なコーポレートブランディングにつなげていく「多メディア展開」を常に視野に入れています。
紙、動画、Web、イベントと、それぞれの手段ごとに、届きやすいターゲットやメッセージは異なります。だからこそ、多角的な媒体でのコミュニケーションを前提とする意識が重要です。“印刷”という出力のプロフェッショナルである私たちは「紙ではどう伝わるか」「ディスプレイ上ではどう見えているか」といった媒体ごとの繊細なアウトプットの調整力にも長(た)けているからこそ、多メディアで展開する際にも、品質を落とさずに対応できるのです。
企業カレンダーを多メディアで展開していくとなると、具体的にはどんな訴求が可能になるのでしょうか。デジタル、アナログ双方のメリットを生かした企画づくりを得意とする川口 真由子は、「クライアントのニーズに合わせて、さまざまな提案が可能だ」と話します。
川口(真):例えば、過去にはカレンダーに採用したイラストの展示会を企画したことがあります。来場していただいた顧客と企業側のリアルなコミュニケーションの場として機能させることで、クライアントが求めていた「顧客とのエンゲージメント強化」のための施策として大きな効果を上げました。
また、別案件ではオリジナルWebサイトを作成して、コンセプト全体の説明や、カレンダーに使用された写真の撮影時のエピソードなど、動画を添えて紹介することもありました。こうしたカレンダーをフックにしたデジタル展開は、紙面に載せきれなかった情報を届けられる余地が格段に広がるため、より深いコーポレートブランディングにつなげる足がかりとなります。
4.変化が加速する時代にこそ、発揮できる価値がある。企業カレンダーのさらなる可能性を求めて
さまざまな年齢層で、それぞれの個性と特技を持ったプロフェッショナルたちが協働する、DCDのカレンダーチーム。彼らの実力が垣間見えたのが、2023年末に発表された「第75回 全国カレンダー展」です。当コンペティションで、3部門すべての経済産業大臣賞、文部科学大臣賞など、金賞をはじめとして、あわせて29件もの賞を獲得。業界内外で大きな話題となりました。この結果について、カレンダー制作歴の長い立川 聰子は「一人ひとりが愛着とホスピタリティを持ってクライアントと向き合えているからこその評価だ」と受け取っています。

立川:企業カレンダーは営業のドアノックツールでもあり、ともすれば“会社の顔”として認識される存在でもあります。6枚、ないしは12枚のカレンダーに、その企業のすべてを詰め込みきる…それくらいの覚悟を持って、チームのみんなが制作に心血を注いでいます。
やっぱり、自分が感動できないものは、見た人を感動させられないと思うんです。だからこそ、コンセプトには寄り添いつつも、必ず自分の心が躍る、うそのないものを作る。そうして出来上がったカレンダーは、暮らしと心を豊かにする力があると信じています。
この言葉に、チームのまとめ役である姫野 美貴が、次のように語ります。
姫野:人々の日常、その365日に自然と馴染(なじ)むメディアは、カレンダーのほかにないと思うんです。住まいに私たちの作ったカレンダーが置かれて、ふと目に入った時に、ちょっと心が休まるきっかけになってくれたらうれしいですね。
技術の進歩とともに、生活のリズムもどんどん加速する世の中だからこそ、カレンダーという媒体が力強く提供できる価値がもっとあるはずだと感じています。これからもそれを真摯(しんし)に考えながら、クライアントを通じて社会の豊かさに寄与し続けられるカレンダーから拡げるコミュニケーションの在り方を模索していきます。
カレンダーチームは、適切にメディアやコンテンツを選び抜く「目利き」、企業と顧客をつなげるストーリーを見いだす「シナリオライター」、アウトプットのクオリティを最大限に引き上げる「職人」、自ら成果物に対してレビューできる「鑑定人」という4つの顔を併せ持ち、メンバーおのおのが企業の真のニーズをけん引する「コミュニケーター」です。
1人ひとりがさまざまなプロフェッショナルの側面を包括的にアップデートしている、DCDのカレンダーチーム。コンセプト設計から印刷の現場まで、トータルでアートディレクションが可能な彼らだからこそ作れる企業カレンダー、彼らと共創するからこそ実現できるコーポレートブランディングがDCDにはあります。
- 2024年5月時点の情報です。
カレンダ―制作支援の情報は以下のWebページでも公開していますので、ぜひご覧ください。



