XRとは? いまさら聞けない!? VR・AR・MRそれぞれの違いと、BtoBビジネスでの活用トレンド
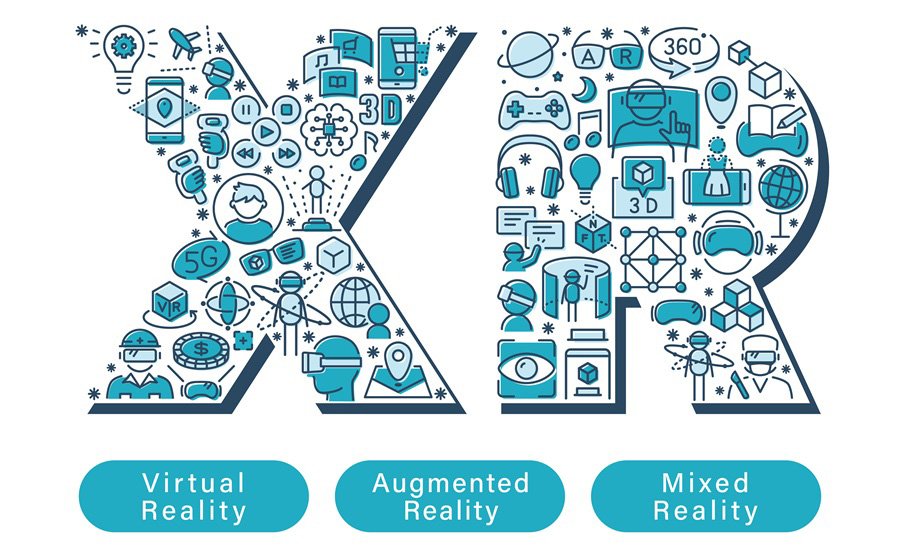
昨今、インターネット上の3次元仮想空間である「メタバース」の話題とともに、メディアなどで目にする機会が増えた「XR・VR・AR・MR」。本記事ではこれらの概念の違いと、それぞれどのようなビジネス活用の可能性があるのかを解説します。
【端的にまとめると】
- 「XR」=現実とデジタルの世界を融合する技術(VR・AR・MRなど)の総称
- 「VR」=現実と切り離されたデジタルの世界に入り込む体験ができる技術(デジタルの世界が主体)
- 「AR」=現実にデジタル情報を付加する技術(現実の世界が主体)
- 「MR」=ARの発展版。現実に表示させたデジタルの情報に干渉できる技術(現実とデジタルが混ざり合う世界)
1. 「XR」とは?――VR・AR・MRをひとくくりに
XR(「xR」と表記されることも)とは「Extended Reality」の略で、「現実とデジタルの世界を融合する技術」の総称です。近年VR・AR・MRに関連する技術が急速に発展し、それぞれが連携して新しい体験価値を生み出す可能性が増してきた背景から、これらを包括する概念として生まれた言葉です。
物理的な制約を超えて、リアルタイムの情報・体験共有を可能にすることで、従来の枠組みを超えた新たなビジネスチャンスを発掘し得るXR。昨今では教育、医療、エンターテインメント、リテール業界などを中心に、さまざまなビジネスシーンでの活用事例が増えています。以下にそれぞれの概念の特徴や違いについて、解説していきます。
2. 「VR」とは?――人を異世界に誘う、没入感重視の体験
VRとは「Virtual Reality」の略で、日本語では「仮想現実」と訳されています。ユーザーはVR対応のデバイスを用いることで、360度広がるデジタル上の空間に没入する体験ができます。VRはこのような仮想の空間、またそれを生み出す技術を指す言葉です。
VRの定義には諸説ありますが、一般的に「人間にとって自然だと感じられる3次元の空間性があること」「実時間との相互作用があること(ユーザーの行動に対して空間が即時に変化する)」「自己投射性があること(ユーザーが実際に空間に入り込んでいる感覚を得られる)」などの条件をクリアした空間だと捉えられています。
VR体験を実現するデバイスにはさまざまなタイプが存在しますが、最も一般的なのは頭部からかぶるようにして装着するヘッドマウントディスプレイです。両目を覆っているゴーグル型のディスプレイの左右にそれぞれ微妙に異なる画像を表示させることで、映像を立体的に出力します。ここに、ユーザーの位置に合わせて映像を制御する「モーショントラッキング」の技術をかけ合わせることで、あたかも仮想空間に入り込んだような体験の提供が可能になります。また、内部にスマートフォンを装着するタイプのVRゴーグルもあり、ヘッドマウントディスプレイがなくても気軽にVRコンテンツを体感することができます。

ユーザーを仮想空間の中に誘い、そこで現実では不可能な体験を提供できるVR。出始めの頃は主にゲームを中心としたエンターテインメントの分野で使われていましたが、医療や教育など、さまざまな業界で活用されるようになってきました。特に昨今では、企業の安全研修において体感型のコンテンツとして活用されるケースが増えてきています。
建設業界では、高所作業や重機の操作など、危険を伴う現場に出る前の研修にVRを活用することで、安全を確保し、命に関わる重要な訓練を行うことができます。従来のトレーニング方法では再現が難しい危険な体験や作業の教育などを、VRを使用することでリアルに体験できるのです。また、ユーザーの行動や判断に対してリアルタイムでフィードバックを提供することが可能です。そのため、作業手順のミスや危険な行動に対して警告を表示し、安全意識を高めることができます。これらの要素は、従来の研修方法では実際の環境再現のために多くの資源やコストが必要でしたが、VRに置き換えることでコスト削減にもつながります。
製造業では、製品や装置の展示会が重要な販促活動の一つですが、リアルな展示会への参加や多くの製品を出展することは、コストや制約があります。そこで、VRを活用することで、自社のWebサイトにバーチャル展示会を常設し、遠隔からでも製品や装置を顧客がリアルに体験できる環境を提供することができます。
また、最近は仮想空間にスマホやPCを使って訪問できるバーチャルショールームを作成することで、遠隔地からでもリアルな会議や商談が可能なコミュニケーションの場が増えています。これにより、3Dモデルやプレゼンテーション資料を共有することもできます。さらに、VR空間では製品の内部構造を見せる演出や製品の説明動画を追加することも可能です。そして、実写版の360度のVR映像を使って実際のショールームをオンライン上に再現したり、逆にCG版では冒険世界のような楽しい表現を演出したりすることもできます。
こうした方法を活用することで、リアルのショールームでは実現できない演出を行うことが可能となります。その結果、顧客やステークホルダーに対して新たな体験価値を提供することができます。
3. 「AR」とは?――空想の世界を現実に映し出す
ARとは「Augmented Reality」の略で、日本語では「拡張現実」と訳されています。スマートグラスと称されるサングラス型のデバイスやスマートフォンなどを用いることで、ユーザーは現実世界にデジタル情報を重ね合わせた視覚体験ができます。ARはこうしたデジタル情報の付加によって拡張した現実、およびそれを可能にする技術のことを指します。
VRはユーザーに現実世界と切り離された「デジタルの世界」を提供するのに対して、ARは「現実の世界」が主体であるという点が大きな違いと言えます。
2016年にリリースされたスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO(ポケモンGO)』などが、ARが活用されたサービスとして最もメジャーな例と言えるでしょう。実際に肉眼で見ている現実の世界に架空の情報が合成され、あたかも目の前に実在するように見せられるのが、ARの大きな特徴です。

ARの種類は、大別すると4タイプに分けられます。あらかじめ登録されたマーカーを認識すると情報が表示される「マーカー型(画像認識型)」、GPSと連携して特定の場所にひもづけられた情報を表示させる「GPS型(位置認識型)」、デバイスのタップアクションが情報提供のトリガーとなる「平面認識型」、特定の3次元の立体物を認識することで情報が表示される「物体認識型」です。ARコンテンツは先に紹介したヘッドマウントディスプレイだけでなく、メガネ型のウエアラブル機器であるスマートグラス、普段使っているスマートフォンなどでも、比較的容易に表示させることができます。
ARのビジネス活用は、特にリテール、製造業、不動産業などの分野で注目されています。リテールにおいては、商品の購入前に「この服を実際に着てみたらどうなるか」「この家具を実際に部屋に置いてみたらどうなるか」といったことをシミュレーションができるARアプリなどが貢献しています。また、企業の製品情報の内部構造を見せる際や、現物展示が難しい製品を社内のショールームで紹介する際などに活用されています。これにより、限られた展示スペースで現物では表現できない製品に対して、ARを活用することで顧客が製品理解を深める手助けをすることができます。
こうしたサービスは生活者や顧客の購買意思決定に寄与し、ユーザーエクスペリエンスの向上や売り上げの増加につながっています。

4. 「MR」とは?――VR×ARで汎用(はんよう)性が広がる
MRとは「Mixed Reality」の略で、日本語では「複合現実」と訳されています。現実の世界に仮想の世界の情報を融合させて、さらには両者が相互に影響し合う空間を生み出す技術のことを指します。イメージとしては、VRとARを組み合わせたような技術とも言えます。
ARは「現実にデジタルの情報を重ね合わせる」だけなので、見えているデジタルの物体を動かしたりすることはできません。一方でMRは、ユーザーの位置や動き、現実空間の形状などをカメラやセンサーで認識することで、映し出したデジタルの物体に干渉できる余地を与えます。

MRを体験できるデバイスは、空間マッピングやハンドトラッキングが可能なヘッドマウントセット、スマートグラスなどが挙げられます。VRでは非透過型のヘッドマウントディスプレイが推奨される一方で、MRの場合は現実世界が見えなければ成立しないため、光学透過型やビデオ透過型を使用する必要があります。
VRとARの特性を併せ持つMRはその汎用(はんよう)性から、多様な業種における業務効率の改善につながり得る技術として注目を集めています。とくにプロダクトの設計やデザインの現場などの情報共有に活用できれば、チーム内での認識のズレが起きにくくなり、コミュニケーションコストの削減が大いに見込めます。
また、MRを社内の教育・研修コンテンツや機器の操作マニュアルに組み込むことも有効的です。平面的な紙のマニュアルだけでは伝えることが困難な煩雑な手順なども、MRでリアルに投影された仮想のオブジェクトを動かしながら覚えれば、直感的に効率よく習得できる可能性が高まるでしょう。
今後、技術の進歩に伴ってデバイスの軽量化・廉価化が進むことを踏まえると、MRの活用の幅はさらに広がっていくことが予想されます。
5. 最後に、それぞれの技術を使う際に何から準備すれば良いか?
VR、AR、MRの活用は、手段の一つです。したがって、まずは目的や実現したいことを明確にするのが最も重要で、次にそれに最適な技術や表現方法を検討します。また、最近ではさまざまなデバイスが登場しています。プロジェクトの規模や特性に応じて、最適なデバイスも異なる場合があります。そのため、この分野の専門家に相談することをおすすめします。
当社では、VR、AR、MRを活用したさまざまなプロジェクトの実績があります。お客さまの目的や実現したいことをお伺いし、最適なデバイスやコンテンツ表現の提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
この記事の担当者は・・・

株式会社DNPコミュニケーションデザイン 第3CXデザイン本部
部長 玉野 真吾/Shingo Tamano
映像プロデューサー/クリエイティブディレクター
業界問わずさまざまな企業を担当し、映像やXRコンテンツを多数制作。高い好奇心と探求心を強みに、国内外での豊富な経験と実績を持つ。最新技術を駆使した展示企画・制作も多く手掛け、ドバイ万博では日本館の金賞受賞(展示部門)に貢献。
- 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 2024年7月時点の情報です。



