コーポレートコミュニケーションの要、企業価値を向上させる「統合報告書」の制作をサポート
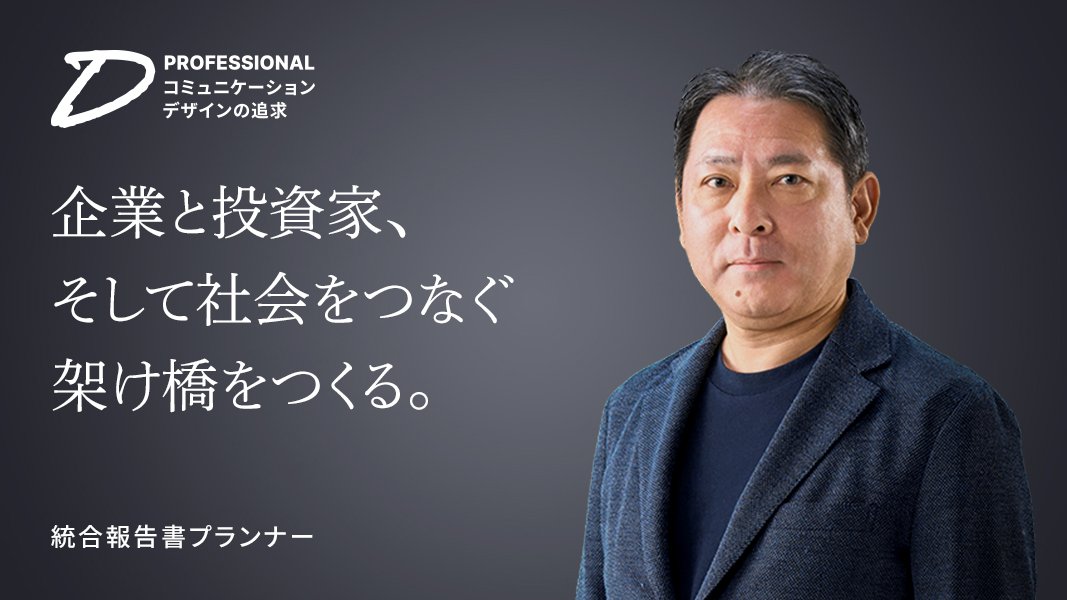
株式会社DNPコミュニケーションデザイン
中部CXデザイン本部
主幹企画員 橋本 智/Satoshi Hashimoto
DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional 」。第4回は、統合報告書の制作サポートに取り組む、中部CXデザイン本部の橋本智です。
【D-Professional】への7つの質問
1. 名前と社歴
よりビジネスの上流へ ― コーポレートブランディングの最前線に至る軌跡
橋本智です。
DCDには2000年に中途で入社しました。少しだけ経歴を補足すると、学生の頃から絵が好きで美大に行きたかったのですが、親からの許しがもらえずに一般大学に進学。その後、新卒で入った会社では営業をやったのですが、どうしてもクリエイティブな仕事に携わりたいという思いが捨てきれず、2年で辞めてデザインの専門学校に入りました。そして卒業後にデザイン会社に転職し、そこからさらに仕事の幅を広げたくて、DCDに入社しました。
はじめはDTPの現場でチラシや旅行パンフレットのデザインを担当していましたが、数年後に「よりビジネスの上流、企画から仕事に携わりたい」という思いが強くなって、自ら希望を出してディレクター職に転向しました。以降、自動車や金融、さまざまな業種でのブランディング案件に関わる中で、統合報告書の制作を相談される機会が増え、今に至ります。

2. 手掛けている業務
企業価値向上のための重点ツール。統合報告書制作の3つのポイント
今、私が所属しているのは、社史や会社案内、企業の公式サイトなど、広くコーポレートコミュニケーションにまつわる案件を担う部署で、その中でも統合報告書の制作をメインとしてサポートしています。
以前は統合報告書というと「グローバルに事業展開をしている企業が海外の投資家対策のために作らなければいけないもの」と、とらえられることが大半でしたが、今ではそうした投資家ニーズに応えるという役割以外にも、「あらゆるステークホルダーに対して自社の強みや将来性をアピールする好機になる」との認識から、近年では企業価値向上のための重点ツールとしてとらえられるケースが増えています。
統合報告書の制作業務は、以下のようなフローで進めていきます。
①前年10月~4月頃にかけて、クライアントから引き合い(コンペへの参加要請)
②オリエンテーション(クライアントから自社の課題、求める支援領域について共有)
③プレゼンテーション(②を踏まえ提案、トレンドに即したレビューと課題の指摘、改善案の提示)
④企画フェーズ(③を踏まえ、課題やニーズに応えながら適切なアドバイスの実施、構成案策定に参画)
⑤制作フェーズ(取材・撮影・原稿作成・制作)
また、統合報告書の制作には主に3つの重要なポイントがあると考えています。
まず1つ目は、年々変化するトレンドと投資家のニーズの把握です。例えば、最近では人的資本経営やDX戦略などが注目されています。そうした時事的な動向、キーワードを的確にとらえてどのように本文に盛り込んでいくか、という検討が必要です。
2つ目は、各機関が出している国際的な開示基準、ESGインデックス、さらには関連法規の動向を把握することです。国内外の動向を注視し、常に最新情報をフォローしながら、新たに対応すべき事項がないか入念にチェックしなければなりません。
そして3つ目は、投資家だけでなく、より幅広いステークホルダーを意識した情報開示です。統合報告書は「作ればOK」ではなく、読んでもらってこそ価値を発揮するもの。正しい手法でまとめられていても、リーダビリティが低ければ本末転倒です。
私たちの部署では、こうした統合報告書の制作におけるコンサルティング領域からコミュニケーション・表現の領域までを、ワンストップでサポートします。経営および投資家層の要点をしっかり押さえ、それをより分かりやすく、適切に情報を届けるための表現の模索に、日々尽力しています。

3. あなたの強みは?
言葉にできないニーズを可視化する「クリエイティブ&コンサルティング」
一言で語るのが難しいですね…「今まで培ってきた知識や経験すべて」が支えてくれているな、という実感があります。
統合報告書の制作とは、会社の歴史や業界についての理解、コーポレートコミュニケーションやブランディングに対する知識、市場や投資家のトレンド把握など、本当に多くの知識とスキルが求められます。私はこれまでにさまざまな業界の案件に携わってきたので、「A社での課題解決のスキームが、少し形を変えればB社でも適応できる」といったように、幅広く積み重ねてきた経験が生きることが多いなと感じています。
また、クリエイティブでの職歴が長いこともあり、コンサルティングをしながらデザイナーとしての職能を発揮できるところに強みがあるかもしれません。対話の中で見えてきたクライアントの言語化しきれていないモヤモヤとした課題や抽象的なニーズを具体的なビジュアルに落とし込み、パワーポイント上にまとめてすぐに見せる…といった小回りのきく対応ができます。
そして、私にできないことがあったとしても、部署のメンバーや社内にいるほかのプロフェッショナルたちが必ずフォローしてくれます。私たちの部署は10年以上前から、アニュアルレポートやCSR報告書なども含めたコーポレートコミュニケーションの業務に携わってきました。経験に裏打ちされたチームとしての総合的な対応力があることは、統合報告書の制作において大きなアドバンテージになっていると思います。
4. 譲れないこだわりは?
イエスマンではないビジネスパートナーに。時に厳しい提言も辞さない姿勢を心掛ける
「ビジネスパートナー」としてクライアントと関わることですね。そのために、言われたことだけを機械的にこなすのではなく、相手の真のニーズや課題の理解に努め、期待値を超えるような一歩踏み込んだ提案をしようと、常々心がけています。また、クライアントに頼れるパートナーとして認めてもらうためには「ただのイエスマンにならない」というのも大事だと思っています。
例えば、「ダイバーシティやサステナビリティ関連の取組みができていないから、そこには触れない内容にしたい」というオーダーがあったとします。けれども、まったく書かないと、特に、海外の投資家には「今、取り組んでいないなら、今後取り組む気もない」と判断される可能性が高まります。
そうならないように、現状できていないことは隠さず開示しつつ、今後の方針や具体的な目標をしっかりと書いていきましょう…といった、相手にとって耳の痛いことも正直にお伝えするよう心がけています。
統合報告書は、中長期的な企業のブランディングに大きく影響するものです。たとえ言いにくいことでも必要なことはしっかりと伝えつつ、クライアントのよりよい未来を見据えて誠実に向き合い、一緒に最善の形を追求する姿勢を大切にしていきたいです。
5. この仕事の醍醐味(だいごみ)は?
企業と投資家、社会をつなぐ架け橋になれる喜び
企業そのものの価値向上にダイレクトに携われるところ、でしょうか。統合報告書は、その内容が投資判断、ひいては株価に大きな影響を与えます。プレッシャーの大きい役割ではありますが、それだけ責任のある業務を信頼して任せてくださっているという事実に、何にも代えがたいやりがいを感じています。

投資家だけでなく世間の人々も、親会社に連なるサプライチェーンの中で不正や人権侵害が起きていないか…というところまで注視するようになってきました。すなわち、統合報告書は上場しているような大企業だけにとどまらず、これからは中小企業でも発行していくものになっていく可能性もあります。
近年のESG投資の広がりや、非財務情報への注目度の高まりなども踏まえると、統合報告書の重要性は、今後ますます高まっていくでしょう。企業と投資家、そして社会をつなぐ架け橋をつくる―そんな意味合いを持っているこの仕事が、私は好きですね。
6. 今後挑戦していきたいことは?
めざすは経営戦略まで踏み込んだアドバイスができるコンサルティング
例えば、クライアントの中期経営戦略の策定などのサポートもできるようになれたらいいな、と思っています。実は最近、あるクライアントから中期経営計画の発表資料作成の依頼を受けたことがあったのですが、単に資料の制作だけでなく、戦略の内容にまで踏み込んだ助言を求められることがありました。
この経験を通じて、私たちの役割がより広がる可能性を感じたんです。統合報告書のベースには、企業の経営戦略が敷かれています。より上流の工程からサポートできる力をつけておけば、今よりもさらにクライアントの価値向上に寄与できるはずです。
もちろん、それは簡単にできることではありません。経営を語るに足る知識や資質を磨き、クライアントに心から信頼してもらえてこそ、任せてもらえる領域だと思います。そんな存在になれるよう、日々の勉強や業界研究を弛まず積み重ねていきたいです。
7. あなたにとってプロジェクトの成功とは?
外部評価と信頼関係、2つの側面から見る成功の形
大きく分けて2つの側面で測れるものと考えています。
まず1つ目は、定量的な評価です。具体的に言うと「日経統合報告書アワード」などをはじめとする外部評価のスコアアップが主な指標になります。このアワードには日本の主要企業の多くが応募していて、私たちも毎年緊張しながらエントリーしています。昨年と比べて結果はどうか、審査員からどのような講評がつくか…といった観点で評価の参考にしています。
2つ目は定性的な側面で「クライアントからパートナーとしてどれだけ信頼されているか」です。普段のやり取りの中でちょっとした困りごとを相談してくださるようになったりすると、「いい仕事ができているな」と感じますね。
ただ、忘れてはいけないのが「統合報告書はコーポレートコミュニケーションのひとつであり、それ単体ですべてが完結するわけではない」という認識です。企業のビジョンやミッションを効果的に伝えるには、ほかの手段も網羅的に活用する必要があります。
コーポレートコミュニケーションの最終的なゴールは、さまざまなステークホルダーに企業を理解してもらい、賛同や共感を得て、ファンになってもらうことです。統合報告書のディレクションを含め、そのゴールに至るまでの道のりを総合的にデザインし、伴走しきれてこそ、真の成功と言えるのではないかな、と考えています。
- 注釈2024年12月時点の情報です。



