「GAを入れただけ」では見えないユーザー(訪問者)の本音 ― 数字の向こう側にある「確かな改善」を見つけ出すウェブ解析士
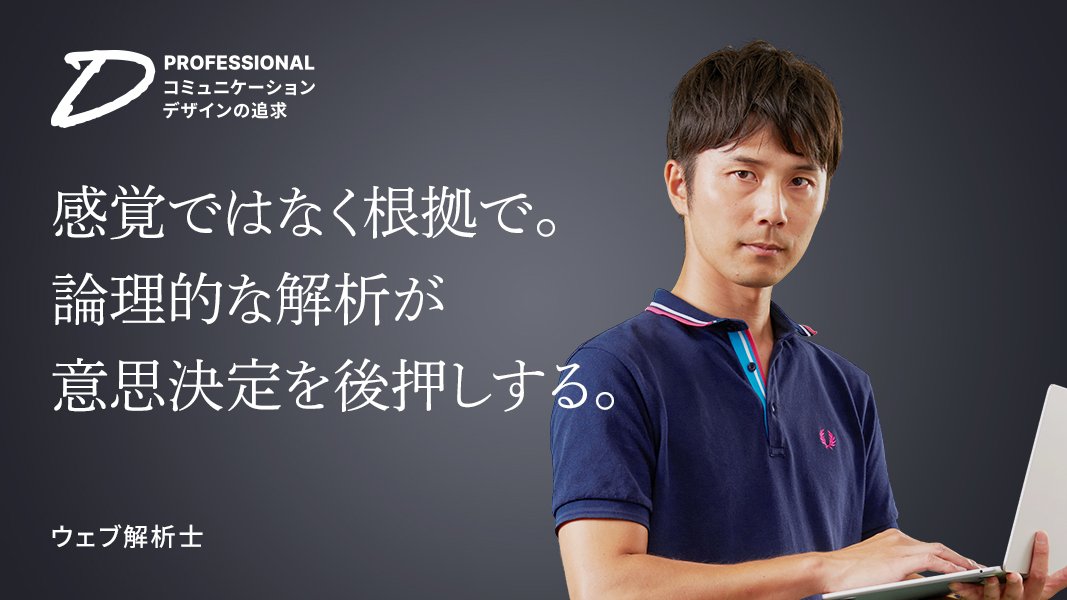
株式会社DNPコミュニケーションデザイン
第3CXデザイン本部
加藤 雅彦/Masahiko Katou
DNPコミュニケーションデザイン(以下、DCD)では、企画・制作における、多くのコミュニケーションのプロが活躍しています。そうしたプロフェッショナルたちにスポットライトを当てる企画、題して「D-Professional」。今回は、Webサイトのデータ分析のエキスパートであるウェブ解析士、第3CXデザイン本部の加藤雅彦です。
【D-Professional】への7つの質問
1. 名前と社歴
映像編集からの転向、適正を生かして解析のプロフェッショナルに
加藤雅彦です。2009年にDNP映像センター(現在はDCDに統合)に入社しました。最初の4年間は映像制作の進行、その後はCG制作などを含めた映像編集の実務を担当していました。
そして、7年前にWeb制作に転向しました。子どもの頃からパソコンには慣れ親しんでいて、就活の時もWeb制作やプログラミングに関わる職種を視野に入れていたんです。以前より「やりたい」が映像、「知識がある」がプログラミング……という認識だったので、映像からWeb制作へのキャリアチェンジは、自分の中では自然な流れでした。
その後、ディレクター業務をする中で徐々にWeb解析の仕事が多くなり、ウェブ解析士の資格を取得。現在はWeb解析がメインの業務になっています。
2. 手掛けている業務
提案と効果測定に、確かな説得力を持たせる専門性
現在の業務は、Web解析を軸にクライアントの課題解決を支援することです。大きく受注前と受注後の2つのフェーズに分かれます。
受注前は、主に「データにもとづく提案の裏付けづくり」が私のタスクです。サイトリニューアル提案などで、既存データを解析して提案に説得力を持たせるための業務を行っています。感覚的に判断するのではなく、数字から仮説を立てて改善案を提案することで、クライアントの意思決定を支援しています。
受注後のメインとなる業務は「効果測定」ですね。LP(ランディングページ)やDMなどの個別の施策ごとの成果を詳細に分析しています。この効果測定が、とても奥深い世界なんです。
GA(Google Analytics:Googleが提供しているWebサイトのアクセス解析ツール)の標準機能をさっと見ただけでは「コンバージョン(以下、CV)した/しなかった」の二元論になりがちです。たとえば「直接的なCVは得られなかったが、そのコンテンツに触れたことで、後々のCVにつながった」という効果もあるかもしれません。スクロール率や滞在時間、ユーザーの行動フローなども視野に入れつつ、解像度を上げた分析をするための調査項目を設計できるのが、Web解析の職能です。
こうした専門性を生かしながら、「解析の設計立案→Tagの埋め込み→成果分析→改善提案」まで一貫してサポートしています。
3. あなたの強みは?
ロジカルで簡潔な「見える化」でデータに親しみを
実務でたたき上げた幅広い業界経験があることです。金融、住宅メーカーをはじめ、これまでに60社以上の企業の案件を担当してきました。業界特有の課題パターンや、BtoBとBtoCでの解析するべき項目の違いなどを把握しています。特にBtoBの案件では、何を成果として設定するべきかがわかりにくいことが多いんです。そういった抽象度の高い課題を、具体的な改善フローに落とし込んでいくノウハウの蓄積だと自負しています。

もう1点挙げるとすると「見える化」の技術です。Web解析は専門的になればなるほど、扱うデータの種類が多くなって、アウトプットも抽象的になりやすいんです。それをわかりやすく伝えるための工夫が重要で、「提案資料では、スライドの1ページで簡潔に可視化すること」「話す順番や構成要素をロジカルに整えること」などを意識しています。
その実例として、大日本印刷株式会社(以下、DNP)の製品・サービスサイトの運営プロジェクトで実施している「コンテンツ通信簿」というものがあります。これはデータ解析に興味関心のない人にも、その重要性を理解してもらうために作った資料で、各所から好評価をもらっています。

かつて映像編集の部署にいた頃、株主総会の映像や資料の作成を担当していたことがあります。そこで培った「膨大な情報をなるべく端的に、わかりやすくビジュアライズする」「単調な資料にならないよう、見せ方を工夫する」という力が、今の仕事に生かされているなと感じています。
4. 譲れないこだわりは?
「わかりやすさ」と「正確性」のはざまで
「事実の歪曲(わいきょく)を絶対に許さない」という姿勢は、何よりも大事にしています。データや数字はロジカルに見えがちですが、だからこそ扱い方を間違えれば、事実が捻じ曲がって伝わる危険性があるんです。
わかりやすさはもちろん大事ですが、それを重視しすぎて正確性を欠くと、間違った現状認識を持たせてしまうかもしれません。そうならないように、常に「わかりやすさと正確性」のバランスをてんびんにかけながら、言葉の選び方、数字の見せ方、グラフ表現に細心の注意を払っています。
5. この仕事の醍醐味 (だいごみ)は?
いつでも正直な「数字」がもたらす学びと楽しさ
数字として成果がはっきりと出てくるところ……でしょうか。Webデザインや施策自体の良しあしは、実際にWeb解析をしてみないとわからないんです。それが明確な形で可視化され、さらに狙い通りの成果が出ていた時には、すごく気持ちがいいですね。
一方で、狙い通りの成果が出ていなくても、データはいろいろな学びをくれます。意外な気付きから新たな改善策が生まれていく過程も、この仕事の楽しみのひとつです。
6. 今後挑戦していきたいことは?
企業活動のすべてを俯瞰(ふかん)して改善できる「データサイエンティスト」に
分析できる領域の拡大です。アプリなどを含めたほかのデジタルチャネルでも専門性を持って分析できるようになれば、さらにクライアントに対して貢献できることが増えるはずです。
将来的には解析ツールとMA(Marketing Automation)ツールを統合したデータプラットフォームを作り、そこでデータ分析ができると理想的だなと考えています。そこまで可能になれば、個別の施策レベルを超えて企業全体の活動を俯瞰した、事業戦略レベルの改善提案ができるかもしれません。
そういったデータサイエンティストのようなアプローチができるように、今後とも貪欲に知識を吸収して、領域を横断するような経験を積み重ねていきたいです。

7. あなたにとってのプロジェクト成功とは?
終わりなき運用、必要なのは「立ち止まらず、改善し続けること」
データ解析をどだいとして、どんな結果が出ても前向きにプロジェクトを動かしていけるような、継続的な改善サイクルを構築できることです。Web解析をやっていると、思惑と異なる結果が出てくることは往々にしてあります。そこで大事なのは、うまくいかなかったことを曖昧にしない心持ちです。
失敗を「ダメなこと」ではなく、「可能性をひとつつぶして、成功に一歩近づいた」ととらえて、立ち止まらずに次の改善に向かっていければ、すべてのプロセスはムダになりません。改善には終わりがないしんどさもありますが、常によりよい打ち手を探求し続けられる面白みもあります。
そういう意識を施策に関わる人たちと共有して、データの力でプロジェクトの成功を後押しし、その上で持続的な成長のメカニズムを育てていくことが、私のウェブ解析士としての最も重要な役割だと思っています。
- 注釈2025年10月時点の情報です。



