パーソナライゼーションイズジャック2:BtoBに立ちはだかる3つの壁と突破口

「パーソナライゼーションはBtoCの話でしょ?」
前回のコラムを読んだ方から、こうしたご意見をいただきました。
→ パーソナライゼーションイズジャック:マーケティング成功の切り札とは?
たしかに従来は、パーソナライゼーションは主にBtoC領域で語られてきました。しかし今、BtoBマーケティングの世界でも注目度が高まっています。その背景には、個人が享受するデジタル体験の進化、生成AIの浸透、そして若手世代の情報価値観の浸透という大きな変化があります。
本コラムでは、まず「なぜBtoBにパーソナライゼーションが不可欠なのか」を整理し、その実現を阻む3つの壁を明らかにします。そしてAIの進展を踏まえつつ、これを突破するための具体的な解決策について論じていきます。
1. BtoBマーケティングにパーソナライゼーションが不可欠な3つの理由
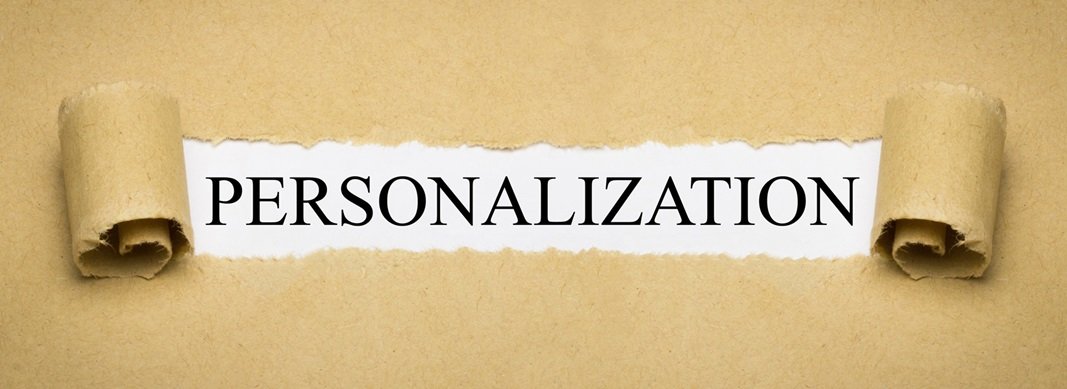
理由①:個人の体験が企業にも波及する現象
私たちは日常生活で、すでに数多くの「パーソナライズされた体験」を当たり前のように受けています。SNSのタイムライン、検索エンジンの結果、ECサイトの商品レコメンド──いずれも個々の行動や好みに合わせて最適化された体験です。
こうした個人としての体験は、そのままビジネスの現場にも持ち込まれると考えています。自分が消費者として便利さや最適化を享受すればするほど、「働く業務環境にも同じ水準を期待する」のは自然な流れです。
実際、過去にはこの動きが「Enterprise2.0」と呼ばれ、Facebook的なつながりを反映した社内SNSや、Google検索の操作感を再現した社内検索エンジンなどが登場しました。
つまり、「日常のパーソナライズ体験を、企業活動の場でも当然視する」というパターンは、今後も繰り返し観測される現象だと考えています。
この“個人体験の企業への波及”という現象に照らせば、BtoBマーケティングにおいても、個人として高度なパーソナライズ体験をした人々は、企業活動の場でも同等レベルの体験を期待するようになるのは必然だといえます。
理由②:AIが引き上げる「パーソナライズ基準」とコンテンツDX

生成AIの普及は、パーソナライゼーションの期待をさらに高めています。私たちはすでにプライベートでChatGPTなどを使い、「自分に合った答えが返ってくる」体験に慣れ始めています。そして便利さを実感するほど、その体験を仕事でも求めるようになるのは自然な流れです。
例えばマーケターが「自社に最適なCX改善ツールを教えてほしい」とAIに聞いてみると、AIは業種特性やターゲット顧客、ビジネス特性などを踏まえて候補サービスを提示し、その公式サイトへのリンクまで添えてくれるでしょう。ところが、そのサイトを開いた瞬間に“一律の機能紹介”しか表示されなければどうでしょうか。高度にパーソナライズされたAIの提案から、いきなりマス向けの体験に逆戻りした感覚を覚え、「本当に自分に合っているのか」と疑念を抱いてしまいます。その落差は違和感を生み、離脱リスクを高めることにもなるでしょう。
実際にAIがWebへの入り口となる流れはすでに加速しています。Adobeの米国での調査(※1)によれば、2024年7月から2025年2月の間、わずか8カ月間でAIアシスタント経由のWebトラフィックは10倍以上に増加しました。
つまり今後は、AIにパーソナライズされたレコメンドを経由してWebに訪れるユーザーが一気に増えるということです。だからこそWebサイト側も、その期待水準に合わせたパーソナライゼーションを実現する必要があります。
理由③:ミレニアル/Z世代がもたらす“情報消費の新常識”
TikTok、Instagram リール、YouTube ショート──ミレニアル世代やZ世代といった若手世代は短尺(たんじゃく)で直感的に理解できるコンテンツに慣れきっています。彼らにとって「自分に関係のない情報」は、一瞬でスワイプされる対象にすぎません。さらにSNS上での体験を通じて、「自分向けに最適化された情報が自然に届く」ことを当たり前と感じています。
重要なのは、この世代がすでにBtoBの購買プロセスに深く関与し始めているという事実です。Forresterのグローバル調査(※2)では、ミレニアル世代とZ世代がすでにBtoBバイヤーの多数派を占め、2022年には64%、2023年には71%に達したと報告されています。
日本は高齢化社会であり、BtoB購買プロセスの意思決定においてはシニア世代が多いのは事実です。しかし、購買プロセスの情報収集や比較検討を担うのは若手世代が中心となりつつあり、欧米と同様の世代交代が進むのは時間の問題といえます。
SNS上でのパーソナライズ体験に慣れた彼らにとっての情報価値は「分量」ではなく「即時性と適合性」にあります。つまり、必要とする瞬間に“自分ごと化”されるコンテンツでなければ、関心を引くことができないのです。BtoBサイトもこの変化に対応しなければ、次世代の意思決定者から瞬時に切り捨てられるリスクを抱えることになります。
2. パーソナライゼーション実現を阻む3つの壁
もちろん、「BtoBにおいてパーソナライゼーションが必要だ」という認識が広がってきたからといって、すぐに実現できるわけではありません。現場で実行に移そうとすると、そこにはいくつもの障壁が立ちはだかります。特に日本企業の現状を踏まえると、大きく3つの課題が浮かび上がってきます。
壁①:把握しづらい企業購買意向
多くの企業では、MAやSFA、CRM、企業データの導入により、基本的な企業属性や担当部署の情報、リードの行動ログは整備されつつあります。
しかし、課題はその先にあります。リード一人ひとりの行動が積み重なった結果として表れるアカウント(企業)全体の購買意向、部署ごとの関与度、そしてリアルタイムに変化する関心テーマといった“動的なシグナルデータ”は、十分に統合・可視化されていないのが実情です。
そのため、アカウント全体を一貫して捉えることが難しく、営業・マーケティング・インサイドセールスがそれぞれ異なる前提でデータを解釈してしまい、結果としてパーソナライゼーションの精度や営業のタイミング判断を損ねています。
壁②:Webパーソナライゼーションの未整備と体験ギャップ
MAやSFAで収集したデータを持っていても、それをWeb体験に活かす基盤は整っていないケースが多く見られます。CMSはもともとWebページの管理が中心の仕組みで、MAはメール配信を目的に作られたツールが多いのが実情です。
そのため、最近ではWebパーソナライゼーション機能を持つものもありますが、根本の設計思想と合わない部分も多く、現場では自分たちだけで使いこなすのが難しい場合もあります。
結果として、メールや広告では個別最適化が進んでいても、Webに来た瞬間に“一律の体験”に戻ってしまうケースが多く見られます。AIレコメンドやSNSを経由して訪問するユーザーが急増する中、この落差は顧客の強い違和感につながりやすくなります。オムニチャネル全体で一貫したパーソナライゼーションを実現しなければ、体験価値は向上せず、このギャップが顧客体験におけるリスクとなります。
壁③:マーケティング現場で完結できないデジタル施策
理想としては「顧客ごとに即座に最適化した体験を提供する」ことが望まれていますが、現実にはCMSやMAの運用にIT部門や外部ベンダーが不可欠です。
AIを中心としたマーケティングテクノロジーの進展、導入が進む中、データを活用した改善も自部門だけでは完結できないケースがまだまだあります。この“デジタル実行ギャップ”が現場の自立性を制約し、俊敏な施策実行を阻んでいます。
Ascend2の米国での調査(※3)でも、71% のマーケターが「自社のマーケティングテクノロジーツールの機能を50%未満しか活用していない」と回答しています。AIが急速に普及する現在、このギャップはますます経営リスクへと直結しています。
結論として、購買意向が見えず、Webは最適化されず、現場は自立できない──この「3つの壁」がBtoBパーソナライゼーションを妨げています。求められるのは、アカウント単位で動的データを補完し、Webを中心としたオムニチャネルで、一貫した顧客体験を現場が自立的に提供できる仕組みです。
3. 解決策:Account-Based Personalization(ABP)プラットフォームの活用
BtoBパーソナライゼーションの3つの壁を乗り越える鍵となるのが、Account-Based Personalization(ABP)プラットフォームです。
従来のMAやSFAがリード単位のデータ管理やメールチャネルでの配信に強みを持つのに対し、ABPプラットフォームはアカウント(企業)単位で、関心・行動データを統合し、営業・マーケティング・インサイドセールス・カスタマーサクセスを横断して一貫した顧客体験を設計できる点に特徴があります。
具体的には以下のように、3つの壁に対して直接的な解決策を提示します。
壁①:把握しづらい企業購買意向
外部の企業属性DBや関心・行動データを既存のMA/CRM基盤に統合し、企業や部署レベルでの関与度や関心シグナルを補完。これにより「どの企業の、どの部署が、いま何に関心を持っているか」を明確に把握できます。
壁②:Webパーソナライゼーションの未整備と体験ギャップ
訪問企業の属性や行動に応じて、セールスコピー/CTA/ビジュアル要素/導線をリアルタイムに最適化。SNSやAIレコメンドで「自分向け」に慣れた顧客体験を、Webでも遜色なく実現します。
壁③:マーケティング現場で完結できないデジタル施策
ノーコード運用を前提に設計されているため、マーケター自身が施策のテスト・反映・改善を高速で回せます。IT部門依存の制約を取り払い、現場に俊敏性を取り戻します。
海外のプロダクト動向
米国では、ABP領域で用途別にプロダクトのすみ分けが進んでいます。
例えば、Mutinyは、Webパーソナライゼーション特化型のABPプラットフォームです。Webページを訪問した企業の業種や規模に応じてセールスコピーやCTAを瞬時に書き換えることを可能にし、ノーコード運用で現場マーケターが自走できる点が評価されています。
一方で、Demandbase Oneは、顧客体験全体を支援するABPプラットフォームで、ターゲットアカウントの特定から広告・Web・営業活動までをシームレスに連動させ、既存のMAやCRMとも統合。アカウント単位で部門を横断した一貫性のある顧客体験を実現しています。
こうした海外プロダクト動向が示すのは、BtoBパーソナライゼーションを阻んできた構造的な課題を、専用のプラットフォームによって実務レベルで解決できるという事実です。日本企業においても、ABPは単なるテクノロジー導入ではなく、パーソナライゼーションを次の段階へと引き上げる重要な手段となるでしょう。

4. まとめ:パーソナライゼーションはBtoBマーケティングの「未来のあたりまえ」
BtoBにおけるパーソナライゼーションは、もはや“選択肢”ではありません。
理由①:個人の体験が企業活動に波及する現象
理由②:生成AIの普及による期待値の急上昇
理由③:ミレニアル/Z世代(若手世代)の即時性、適合性を求める情報消費スタイル
これら3つの理由により、顧客は「自分に合った情報が提示されること」を前提に企業サイトを訪れています。
しかし現実には、
壁①:把握しづらいアカウント購買意向
壁②:Webパーソナライゼーションの未整備と体験ギャップ
壁③:マーケティング現場で完結できないデジタル施策
これら“3つの壁”が立ちはだかり、多くのBtoBサイトはいまだに一律情報を出し続けています。
こうした課題を突破する解の一つがAccount-Based Personalization(ABP)プラットフォームです。海外ではすでに、ABPの導入が進み、パーソナライゼーションを実務レベルに落とし込む動きが広がっています。日本企業にとっても、これは遠い未来ではなく、今まさに備えるべき局面です。
生成AIを経由した流入が急増するなかで、もしWeb体験がユーザーに最適化されていなければ、ユーザーはためらうことなく他社を選ぶでしょう。
BtoBにおいても、パーソナライゼーションは特別な施策ではなく、企業が選ばれ続けるための前提条件です。そして、視点をさらに広げれば、ABPはあくまでゴールではなく、Account-Based Experience(ABX)を実現するための手段にすぎません。企業全体で一貫した顧客体験を設計・提供することこそが、最終的に競争優位を生み出す鍵となります。
- 注釈1Adobe, The explosive rise of generative AI referral traffic, 2025年3月17日
- 注釈2Forrester, Younger Generations Are Shaking Up B2B Buying, 2024
- 注釈3Ascend2 “The Future of the Martech Stack”, 2022
株式会社DNPコミュニケーションデザイン コンテンツDX本部
小野 友剛/Tomotake Ono
マーケティングDXストラテジスト
外資系DWHベンダーや日本のSIerで営業・マーケティングDXを推進し、戦略立案からシステムの導入、実行までを経験。その後、DNPで事業部のマーケティングDX戦略の策定・実施、推進を担当し、DX革新の旗振り役も担う。全体戦略、ジャーニー策定、サイト企画、コンテンツ戦略など上流を中心に推進。CMS・MA・BI・マーケティングデータなどのツール選定・導入を行い、自社の経験を生かして顧客企業への営業も推進する。MAを活用したリードジェネレーション/ナーチャリングやインサイドセールス部門との連携による営業最適化も推進。
- 注釈2025年10月時点の情報です。



